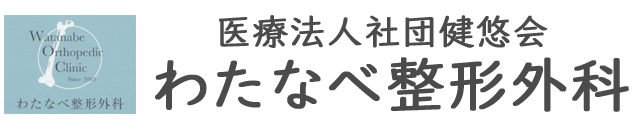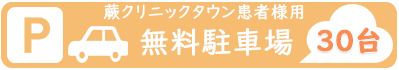リハビリスタッフコラム
2025.9.11
久しぶりに研修会に参加してきました!
去る9月4日(木)、私が所属しています「埼玉県理学療法士会」が主催した研修会に参加してきました。
今回は「腰痛症に関する徒手療法」と題しまして、腰痛症に対しての講義と手技に関する内容でした。
職歴が40年を超える大ベテランの先生が講師を務めていただき、腰痛症に対する知識の整理と
治療手技の勉強になりました。
勉強してきた内容が、症状の改善に繋がるように日々努力していきたいと思います。
因みに…
こういった専門職向けの研修会・講習会は、所属している協会を中心に様々なところで開催されており、
その数は開催場所を全国で検索すると500件以上になります。
(更に協会以外を含めたら、1000件は超えてくるものと思われます。)
当然全てには参加できませんし、その内容も(整形外科で担当する)“運動器疾患” 以外もありますので、
内容を確認したうえで申し込みをすることになります。
近代医学の父と呼ばれた「ウィリアム・オスラー」医師の言葉に…
「医師は一生を通じて学生である」
という言葉があります。
これは、終生学習の姿勢を医療者に求めた言葉と言われています。
経験年数が何年あっても、(残念ながら…)学ぶことは沢山あります。
学ぶ姿勢をこれからも持ち続けたいと思います。
【PT:H.K】
(イラストは生成AIが作成したイメージです)
2025.7.13
個人的には「いい買い物」となりました!
「本当に梅雨は終わっていないのか?」と思ってしまうほどの暑い7月を迎えていますが、
皆様、いかがお過ごしでしょうか?
くれぐれも来院の際には、熱中症にならないように対策をしっかり行っていただき、
十分にご注意ください。
私事ですが、つい最近ハンディファンと呼ばれている“ミニ扇風機”を購入しました。
以前から人気があり様々なところで売られているのは知っていましたが、
「あんなちっちゃい扇風機でどうなんだろうか?」という思いがあり、購入したことがありませんでした。
家族に勧められて半信半疑で購入して使ってみましたが…、おぉ、以外にも涼しい!
屋外作業をされている方の多くが使用している空調服という商品も同様ですが、汗をかいて皮膚表面が
濡れている状況で風を当てることで、気化熱を利用して体温を下げることになりますので、
汗っかきな私には「いい買い物」となりました。
日本には昔から扇子という便利なものがあり、これも同様の効果を得るものですが、やはり自動で風を
送ってくれる点は、嬉しい限りです。
(充電式なので、充電を忘れないように注意したいと思います!)
【PT:H.K】
2025.5.11
筋肉ってなんで必要なのでしょうか?①
様々なところで「筋肉を鍛えましょう!」という言葉を見聞きすることが多いと思いますが、
そもそも筋肉ってなんで必要なのでしょうか?
一番大切な理由といえば「人間が地球上で動くために必要な力を生み出すから」です。
地球には重力という力があります。人間はこの重力に負けないように立って、歩いて行動をしています。
もしもこの重力に負けてしまうと、歩けなくなり、立てなくなり、座っていられなくなり、最終的には寝たきりという状況になってしまいます。
特に鍛えるべき筋肉は、「抗重力筋(こうじゅうりょくきん)」と呼ばれる、“重力に抗して働く筋肉”です。
具体的には、脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)、腹直筋(ふくちょくきん)、腹斜筋(ふくしゃきん)、
大殿筋(だいでんきん)、大腿四頭筋(だいたいしとうきん)、下腿三頭筋(かたいさんとうきん)などです。
(*抗重力筋については、文献などによって多少の違いがあります)
これらの筋肉を鍛えるようにしましょう。
筋肉の図に関してはこちらを参考にしてみてください。→【抗重力筋】(新しいタブが開きます)
2025.4.20
杖はどちらの手に持ちますか?
「杖はどちらの手に持ってもいいのですか?」というご質問がありました。
確かに、“杖をどちらの手に持つか?”という答えをご存じない方も多いと思います。
答えは…
「良い足側の手に持つのが正解です!」となります。
片方の足が痛かったり悪かったりした場合、そちらを「患側(かんそく)」と呼びます。
逆に良い足の方を、「健側(けんそく)」と呼びます。
通常は、健側の手に持って歩くようにします。
これは、普通の杖だけでなく片側の松葉杖を使用する場合も同じです。
実際に使ってみていただくとわかりやすいと思いますが、人が歩くときは反対の手と足が同時に前に出ます。
右足が患側であれば、“右足”を前に出すときは健側の手である“左手”を前に出しますよね。
こうすることで、患側である右足で体重を支える時に健側の手である左手の杖で支えることになります。
(わかりますか?…、ちょっとややっこしいですかね?…)
また、階段などの手すりを使用する場合も同じ方法で使用していただけば、歩きやすいと思います。
もしも健側・患側がなく、単にバランスが悪いために杖を使用する場合は、決まった側はありませんので、
持ちやすい方で結構です。
手をケガしていたり通常の杖が使用できないなどの場合は、医師・看護師・理学療法士などにご相談して
いただいた方が良いと思います。
2025.3.3
運動習慣を獲得する方法とは?
「『ウォーキングやストレッチ、筋力トレーニングなどの運動習慣を身につけましょう』とアドバイスされても、
なかなか習慣化しないんです…」というお話をお聞きする機会が多々あります。
必要だとは思っていても、“なかなかやる気が起きない…”という状況ですね。
そういう時の対処法をお教えしましょう!
それは、「まずは4分間だけで良いでやってみる!」という方法です。
アメリカの心理学者レナード・ズーニンが提唱したもので、「ズーニンの法則」や「初動4分の法則」などと呼ばれています。これは「最初の4分間だけ頑張ると、その後も自然とやる気が続く」というもので、人間は、行動を始めるまでに最も大きなエネルギーが必要ですが、一度始めるとその勢いを保ちやすくなるという性質があるそうです。
この法則は、脳の活動としては報酬系や快感に深く関与していると言われています。人間は、何かを始めることで前脳基底部にある側坐核(そくざかく)が活性化しドーパミンが分泌されます。このドーパミンは、行動を起こす原動力として働くためモチベーションを向上させ、そこから得られた成功体験が更なるドーパミンの分泌を促し、さらなる行動を引き出すと考えられています。
この法則では、「やる気を出して ⇨ 行動力を得る」のではなく、「行動を起こすと ⇨ やる気が出る」という事を示しており、そのためには「最初の4分間が重要である」とされています。
最初は「4分間だけの実行」でも良く、実行できたという成功体験が大切であり、そこから徐々に実施時間などを伸ばせていけたらバッチリという訳です。
またこの法則は運動習慣に限らず、勉強や仕事などでも効果が期待できるそうなので、様々な“やる気がでない場面”で、役立ててみてはいかがでしょうか。
2025.2.3
認知症予防として簡単にできるものとは?
認知症予防としては「脳を使うと良い」と言われています。
では、脳を使うとは具体的に何をすれば良いのでしょうか?
答えは「運動をしながら考える事」が良いとされています。
今からすぐに実践可能なものとしては…
ズバリ‼「散歩しながらお喋りをする」事です。
運動(歩くこと)をしながら、会話(相手の話を聞いて考えて喋ること)をすると、
2つの事柄を行うために脳を活用する事になります。
歩くだけでも、筋肉に命令を発信したりバランスを保持したりと脳は使われますが、
これに考える事を追加することで脳は更に働かないといけなくなります。
この刺激が、脳を活性化させるのに有効と言われています。
筋肉や柔軟性の向上には、筋トレや柔軟体操など身体に刺激を与える事が必要となりますが、
脳にも同様に適度な刺激を与える事が大切です。
それが「運動+考える」という行動で、与える事ができます。
「国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター」が開発した認知症予防運動の方法に
「コグニサイズ」というプログラムがあります。これは軽い運動をしながら頭で計算やしりとりをするものです。
インターネット上でも、具体的なやり方などが紹介されていますので「コグニサイズ」で検索して、
参考にしてみてください。
2025.1.3
「セデンタリー」という言葉をご存知ですか?
「セデンタリー(Sedentary)」とは、英語で「座りがち」という意味の言葉です。
オーストラリアの研究機関の調査では、日本人の平均座位時間(座っている時間)は約7時間で、これは調査した20ヶ国の平均の約5時間を大幅に超える時間となっています。
座り続けることで血流や筋肉の代謝が低下し、心筋梗塞、脳血管疾患、肥満、糖尿病、がん、認知症など健康に害を及ぼす危険性が指摘されています。
1日に座っている時間が4時間未満の成人と比べ、1日に11時間以上座っている人は死亡リスクが40%も高まるといわれ、2011年、WHO(世界保健機関)によれば、「世界で年間200万人の死因になる」という発表もあります。
なるべく長時間座っている状況は避けるように、立ち上がって歩くなど、身体を動かすようにしましょう。
⇨
2024.12.2
お出かけをしたいけど歩くのが不安だったり、転倒が心配だったりする方もいらっしゃるのではないでしょうか。
令和元年に厚生労働省が行った調査によると、介護が必要になった主な原因の中で、「骨折・転倒」は13%を占めるそうです。
特にご高齢の方では、骨密度の低下や筋力・バランス能力の低下から転倒リスクが高くなります。
転倒リスクが高い状態を改善するには、日常的な運動による筋力・バランス能力の向上や骨粗鬆症の治療が有効です。
『運動をしたいけど、何をすればいいかわからない』
『痛いところがあるのに、さらに悪くしてしまいそうで怖い』
等の理由で、やってみたいけどなかなか運動に踏み出せないという方も多いのではないでしょうか。
当院では、転倒リスクが高くなった方に対し、理学療法士が個別的に運動指導を行っています。痛みの程度やそれぞれの方の不安を確認しながら実施させていただきますので、ご希望の方がいらっしゃいましたら、当院スタッフまでお声掛けください。
また、当院では骨密度検査も実施できますので、気になる方は受診の際にご相談ください。
(理学療法は症状の程度や疾患によって実施できないこともございますのでご了承ください。)
➡
➡